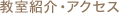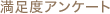カテゴリ
月別 アーカイブ
- 2025年4月 (7)
- 2025年3月 (66)
- 2025年2月 (59)
- 2025年1月 (61)
- 2024年12月 (64)
- 2024年11月 (65)
- 2024年10月 (67)
- 2024年9月 (65)
- 2024年8月 (62)
- 2024年7月 (66)
- 2024年6月 (67)
- 2024年5月 (65)
- 2024年4月 (63)
- 2024年3月 (64)
- 2024年2月 (56)
- 2024年1月 (52)
- 2023年12月 (54)
- 2023年11月 (55)
- 2023年10月 (53)
- 2023年9月 (54)
- 2023年8月 (54)
- 2023年7月 (57)
- 2023年6月 (62)
- 2023年5月 (76)
- 2023年4月 (89)
- 2023年3月 (85)
- 2023年2月 (69)
- 2023年1月 (69)
- 2022年12月 (70)
- 2022年11月 (65)
- 2022年10月 (51)
- 2022年9月 (44)
- 2022年8月 (20)
- 2022年7月 (35)
- 2022年6月 (37)
- 2022年5月 (37)
- 2022年4月 (50)
- 2022年3月 (42)
- 2022年2月 (51)
- 2022年1月 (37)
- 2021年12月 (42)
- 2021年11月 (41)
- 2021年10月 (37)
- 2021年9月 (20)
- 2021年8月 (25)
- 2021年7月 (28)
- 2021年6月 (20)
- 2021年5月 (27)
- 2021年4月 (83)
- 2021年3月 (59)
- 2021年2月 (15)
- 2021年1月 (36)
- 2020年12月 (44)
- 2020年11月 (46)
- 2020年10月 (47)
- 2020年9月 (39)
- 2020年8月 (47)
- 2020年7月 (73)
- 2020年6月 (77)
- 2020年5月 (26)
- 2020年4月 (53)
- 2020年3月 (84)
- 2020年2月 (35)
- 2020年1月 (29)
- 2019年12月 (36)
- 2019年11月 (34)
- 2019年10月 (35)
- 2019年9月 (29)
- 2019年8月 (26)
- 2019年7月 (46)
- 2019年6月 (68)
- 2019年5月 (86)
- 2019年4月 (111)
- 2019年3月 (143)
- 2019年2月 (88)
- 2019年1月 (90)
- 2018年12月 (101)
- 2018年11月 (52)
- 2018年10月 (64)
- 2018年9月 (70)
- 2018年8月 (96)
- 2018年7月 (80)
- 2018年6月 (49)
- 2018年5月 (50)
- 2018年4月 (48)
- 2018年3月 (53)
- 2018年2月 (36)
- 2018年1月 (48)
- 2017年12月 (36)
- 2017年11月 (48)
- 2017年10月 (55)
- 2017年9月 (58)
- 2017年8月 (65)
- 2017年7月 (88)
- 2017年6月 (97)
- 2017年5月 (107)
- 2017年4月 (109)
- 2017年3月 (117)
- 2017年2月 (104)
- 2017年1月 (95)
- 2016年12月 (69)
- 2016年11月 (4)
- 2016年10月 (5)
最近のエントリー
HOME > 教室長ブログ > 富士見ヶ丘教室 > 9/14 【富士見ヶ丘教室】時間の使い方考察
富士見ヶ丘教室
< 9/13【久米川教室】社会を得意にするためには | 一覧へ戻る | 9/15【富士見ヶ丘教室】学習環境づくり >
9/14 【富士見ヶ丘教室】時間の使い方考察
大事な大事な三連休。無駄な時間の使い方をしていないでしょうか?
勉強が苦手なお子さんに総じて言えることが、時間の使い方がうまくないということ。
朝も起きるのが遅い、起きてからダラダラしているなどの割合が高いのでは?と思います。
病気の場合を除いては、総じて目的意識が低いことが原因として挙げられます。
「朝から勉強しなくては!」と意識の高いお子さんは、たとえ眠くてもそこは意を決して起き上がるものです。
スマホにしてもしかりです。スマホは中毒性が高いものです。
一度沼にはまると、スマホを手離すことが難しくなり、親に隠れてでも見てしまうなど、自制心が効かなくなり行動がエスカレートしていきます。
一方、目的意識が高いお子さんは、スマホへの優先度が高くなくなるため、あっさりと手放したり、電源を切ったりできます。
試験時の「目標に対する意識」を高めていくだけで、お子さんの動きは格段に変わります。
その意識づけの方法は、お子さんによってさまざまです。私自身お子さんと接しながら、どうすることで目的意識を持つようになるかを考えています。
今日ダラダラ朝を過ごしていたお子さん、スマホから離れられないお子さんは、明日こそはそれを回避する行動ができるようにしていきたいものです。
勉強が苦手なお子さんに総じて言えることが、時間の使い方がうまくないということ。
朝も起きるのが遅い、起きてからダラダラしているなどの割合が高いのでは?と思います。
病気の場合を除いては、総じて目的意識が低いことが原因として挙げられます。
「朝から勉強しなくては!」と意識の高いお子さんは、たとえ眠くてもそこは意を決して起き上がるものです。
スマホにしてもしかりです。スマホは中毒性が高いものです。
一度沼にはまると、スマホを手離すことが難しくなり、親に隠れてでも見てしまうなど、自制心が効かなくなり行動がエスカレートしていきます。
一方、目的意識が高いお子さんは、スマホへの優先度が高くなくなるため、あっさりと手放したり、電源を切ったりできます。
試験時の「目標に対する意識」を高めていくだけで、お子さんの動きは格段に変わります。
その意識づけの方法は、お子さんによってさまざまです。私自身お子さんと接しながら、どうすることで目的意識を持つようになるかを考えています。
今日ダラダラ朝を過ごしていたお子さん、スマホから離れられないお子さんは、明日こそはそれを回避する行動ができるようにしていきたいものです。
カテゴリ:
(TOMAN)
< 9/13【久米川教室】社会を得意にするためには | 一覧へ戻る | 9/15【富士見ヶ丘教室】学習環境づくり >