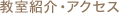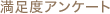カテゴリ
月別 アーカイブ
- 2025年4月 (8)
- 2025年3月 (66)
- 2025年2月 (59)
- 2025年1月 (61)
- 2024年12月 (64)
- 2024年11月 (65)
- 2024年10月 (67)
- 2024年9月 (65)
- 2024年8月 (62)
- 2024年7月 (66)
- 2024年6月 (67)
- 2024年5月 (65)
- 2024年4月 (63)
- 2024年3月 (64)
- 2024年2月 (56)
- 2024年1月 (52)
- 2023年12月 (54)
- 2023年11月 (55)
- 2023年10月 (53)
- 2023年9月 (54)
- 2023年8月 (54)
- 2023年7月 (57)
- 2023年6月 (62)
- 2023年5月 (76)
- 2023年4月 (89)
- 2023年3月 (85)
- 2023年2月 (69)
- 2023年1月 (69)
- 2022年12月 (70)
- 2022年11月 (65)
- 2022年10月 (51)
- 2022年9月 (44)
- 2022年8月 (20)
- 2022年7月 (35)
- 2022年6月 (37)
- 2022年5月 (37)
- 2022年4月 (50)
- 2022年3月 (42)
- 2022年2月 (51)
- 2022年1月 (37)
- 2021年12月 (42)
- 2021年11月 (41)
- 2021年10月 (37)
- 2021年9月 (20)
- 2021年8月 (25)
- 2021年7月 (28)
- 2021年6月 (20)
- 2021年5月 (27)
- 2021年4月 (83)
- 2021年3月 (59)
- 2021年2月 (15)
- 2021年1月 (36)
- 2020年12月 (44)
- 2020年11月 (46)
- 2020年10月 (47)
- 2020年9月 (39)
- 2020年8月 (47)
- 2020年7月 (73)
- 2020年6月 (77)
- 2020年5月 (26)
- 2020年4月 (53)
- 2020年3月 (84)
- 2020年2月 (35)
- 2020年1月 (29)
- 2019年12月 (36)
- 2019年11月 (34)
- 2019年10月 (35)
- 2019年9月 (29)
- 2019年8月 (26)
- 2019年7月 (46)
- 2019年6月 (68)
- 2019年5月 (86)
- 2019年4月 (111)
- 2019年3月 (143)
- 2019年2月 (88)
- 2019年1月 (90)
- 2018年12月 (101)
- 2018年11月 (52)
- 2018年10月 (64)
- 2018年9月 (70)
- 2018年8月 (96)
- 2018年7月 (80)
- 2018年6月 (49)
- 2018年5月 (50)
- 2018年4月 (48)
- 2018年3月 (53)
- 2018年2月 (36)
- 2018年1月 (48)
- 2017年12月 (36)
- 2017年11月 (48)
- 2017年10月 (55)
- 2017年9月 (58)
- 2017年8月 (65)
- 2017年7月 (88)
- 2017年6月 (97)
- 2017年5月 (107)
- 2017年4月 (109)
- 2017年3月 (117)
- 2017年2月 (104)
- 2017年1月 (95)
- 2016年12月 (69)
- 2016年11月 (4)
- 2016年10月 (5)
最近のエントリー
HOME > 教室長ブログ > 大泉南教室 > 勉強の順番(大泉南教室)
大泉南教室
< 今週の土曜日は??(石神井台教室) | 一覧へ戻る | 「言ってはいけない」という本 >
勉強の順番(大泉南教室)
多くの中学生は「問題を解くこと」だけが勉強だと勘違いしています。
よく考えればわかると思うのですが、そもそも
「覚えていないもの・知らないもの」は解ける訳がありませんよね。
「先生、これってどうやって解くんですか?」
「ちょっと見せて。まずさ、これを解くときの公式は?」
「…覚えてません…」←そりゃ出来んわい!
先日も山脈や川の位置を覚えていないのに地理ワークをやろうとしている子がいましたね…
もちろん、その場で止めました。
問題を解く前に、まず「問題を解ける状態を作る」ことが、勉強のスタートラインなんです!
間違っても演習から始めてはいけません。
演習から始めていいのは、学校の授業がすでに頭に入っている子だけ!
ですから勉強は
①に理解
②に暗記
③に演習
④に反復
これが黄金パターンです。
まずは学校のノートと教科書を見直し、必要な部分をまとめ、それらを頭に入れる。
そこで生まれた疑問は必ず質問をして解決する。
そして、ある程度頭に入ったら、ようやく問題演習へゴー!
その後、演習で発見した不十分だった箇所を復習し、補強したら次の演習へ!
あとはこの繰り返しです。
ってな訳で、せっかくやるのだから、ちゃんと効率の良い順番で勉強をしましょうね!
よく考えればわかると思うのですが、そもそも
「覚えていないもの・知らないもの」は解ける訳がありませんよね。
「先生、これってどうやって解くんですか?」
「ちょっと見せて。まずさ、これを解くときの公式は?」
「…覚えてません…」←そりゃ出来んわい!
先日も山脈や川の位置を覚えていないのに地理ワークをやろうとしている子がいましたね…
もちろん、その場で止めました。
問題を解く前に、まず「問題を解ける状態を作る」ことが、勉強のスタートラインなんです!
間違っても演習から始めてはいけません。
演習から始めていいのは、学校の授業がすでに頭に入っている子だけ!
ですから勉強は
①に理解
②に暗記
③に演習
④に反復
これが黄金パターンです。
まずは学校のノートと教科書を見直し、必要な部分をまとめ、それらを頭に入れる。
そこで生まれた疑問は必ず質問をして解決する。
そして、ある程度頭に入ったら、ようやく問題演習へゴー!
その後、演習で発見した不十分だった箇所を復習し、補強したら次の演習へ!
あとはこの繰り返しです。
ってな訳で、せっかくやるのだから、ちゃんと効率の良い順番で勉強をしましょうね!
カテゴリ:
(TOMAN)
< 今週の土曜日は??(石神井台教室) | 一覧へ戻る | 「言ってはいけない」という本 >